たけのこの漢字はどう書く?「竹の子」と「筍」の違いは?由来・成り立ちなど紹介!
たけのこの漢字はどう書くか知っていますか?今回は、たけのこの漢字<筍・竹の子・笋>の由来・意味に加えて、「筍」と「竹の子」の違いも紹介します。〈ふき〉など、たけのこ以外の山菜の難読漢字についても紹介するので、参考にしてみてくださいね。
目次
たけのこの漢字③「笋」

たけのこを表す漢字には笋もありますが、これは当て字です。そのため、常用漢字には含まれていません。ここでは、笋の漢字の由来と意味を詳述します。
「笋」の漢字の由来・意味
笋も竹の若芽を意味する言葉で、由来はたけのこの古名にあたるたかんなです。一般的な読み方はじゅんで、当て字としてたけのこと読まれることもある程度なので、基本的にあまり使われることがない感じとなっています。
たけのこ以外の山菜の難読漢字は?
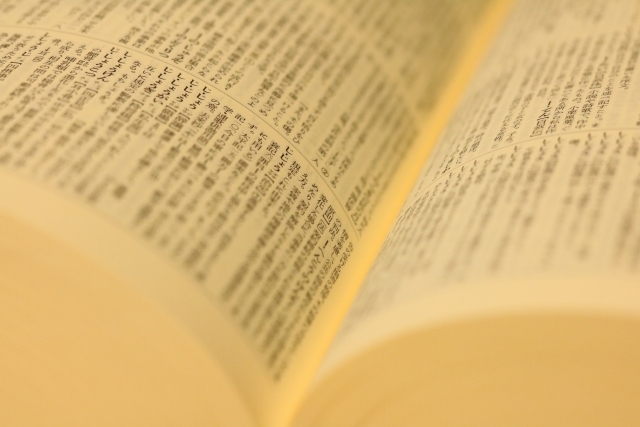
山菜の漢字表記を見ていると、難しいものが多いことに気がつきます。ここでは、たけのこ以外の山菜の難読漢字を3つ紹介します。
①ふき:蕗

出典: @arthurclaris
日本が原産の山菜であるふきは、蕗と書きます。蕗は会意兼形成文字が由来となっており、並んで生えている草と人間の胴体、立ち止まり下向きになっている足、口を組み合わせて作られた漢字です。画像はフキノトウですが漢字の成り立ちにうなずけるものがあり、土手や川辺など人間に身近な道の傍らに生えるという意味も、あわせ持つと考えられます。
②こごみ:草蘇鉄

出典: @kopa0616
河川敷や山地の中でも湿った場所に生えるこごみは、漢字では草蘇鉄と表します。これは、こごみの葉が常緑木であるソテツの葉と形状が似ていることが由来です。こごみと呼ばれるようになった理由は、芽がうずくまりこごんでいるように見えることとされています。
③うど:独活

出典: @takao_camera
天ぷらや酢味噌和えにして食べられることの多いうどは、漢字で独活と書きます。由来は中国とされており、うどは風がなくても1人で揺れているように見えることから、独りで活動するが省略されて独活になったようです。
画像はうどの花ですが、確かに風で揺れていそうです。食用のうどは30cm程度ですが、山野に自生しているものはは花が付く頃には1.5m以上になることも珍しくありません。
(*他の野菜の漢字の読み方について詳しく知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。)
