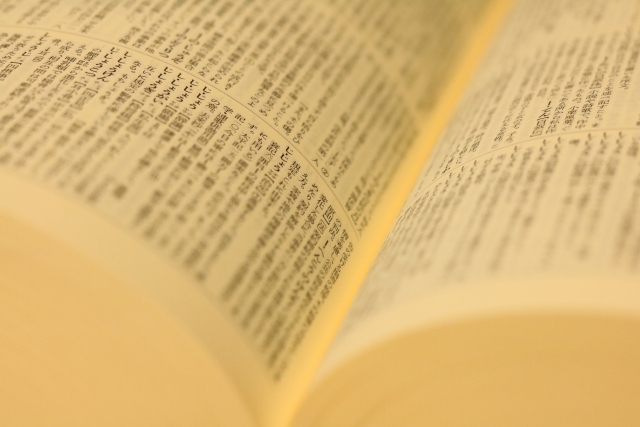キャベツを漢字で書くと「甘藍」「玉菜」のどっち?由来・意味やロールキャベツの漢字表記なども紹介!
キャベツを漢字でどう書くか知っていますか?今回は、キャベツの漢字は「甘藍」or「玉菜」のどっちかや、由来や意味についても紹介します。ロールキャベツの漢字や〈レタス・ピーマン〉など、キャベツ以外の野菜の難読漢字も紹介するので、参考にしてみてくださいね。
(このページにはPRリンクが含まれています)目次
キャベツを漢字で書くと?

キャベツは普段はカタカナ表記が基本なので、漢字がわからない人も多そうです。また、キャベツの漢字表記は2種類ありますが、どちらが正しいのかも気になるところです。ここでは、キャベツの漢字表記について、由来も含めて詳述します。
キャベツの漢字表記は「甘藍」or「玉菜」どっち?

キャベツの漢字表記について調べてみると、甘藍と玉菜の2つがあることがわかりました。漢字表記が複数ある食材はたくさんありますが、キャベツは意味が異なるようです。ここでは、キャベツの漢字表記は甘藍と玉菜ではどちらが適切なのかを説明します。
キャベツの漢字・別名は「甘藍(かんらん)」
キャベツの漢字表記は、甘藍(かんらん)が正しいです。食用キャベツのことを漢字で、甘藍と表記します。甘藍は中国語なのですが、呼称であるキャベツが定着するまでは、ずっとその名前で呼ばれていました
「甘藍」の漢字の意味は葉牡丹

中国において甘藍はキャベツだけでなく、葉牡丹の古名としても使われています。日本ではかんらんと読みますが、中国語ではピンインです。そもそも鑑賞用の植物である葉牡丹の漢字として使われていた甘藍が、キャベツを表すようになったことには意味があるので、次章で詳述します。
「甘藍」の漢字の由来はキャベツが初め観賞用だったから
キャベツの漢字表記として「玉菜」がありますが、これは食用キャベツではなく、鑑賞用のものを意味しています。日本に初めてキャベツが伝わったのは江戸時代で、オランダから持ち込まれたものでした。当時のキャベツは現在のような球形でも、食用でもなかったのです。
また鑑賞のキャベツは見た目が葉牡丹と似ていたこともあり、甘藍と呼ばれるようになりました。
ちなみにロールキャベツの漢字はどう書くの?

キャベツを甘藍と書くとわかると、ロールキャベツも漢字表記ができるのかが気になる人もいそうです。ここでは、ロールキャベツの漢字表記を紹介します。
ロールキャベツの漢字は「巻甘藍」
ロールキャベツは漢字で、巻甘藍と書きます。キャベツ葉で具材であるひき肉を巻いてつくる状態を、そのまま漢字表記としています。漢字で書く機会は少ないと思いますが、知識として覚えておきましょう。
キャベツ以外の野菜の難読漢字はある?