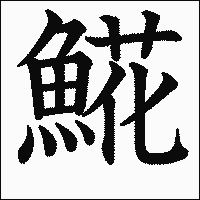魚へんに花「𩸽」と書いて何と読む?由来は?他に魚へんがつく漢字は?
魚へんに花という漢字を書いてなんと読むか知っていますか?読み方は「ホッケ」です。今回は、魚へんに花で「ホッケ」と読む由来をホッケの特徴とともに紹介します。「䱅」など、魚へんがつく漢字の魚をホッケ以外にも紹介するので参考にしてみてくださいね。
(このページにはPRリンクが含まれています)目次
魚へんに花という漢字を書いて何と読む?読み方・由来は?
魚へんの漢字には、多く読み方の解らない文字があります。ここでは魚へんに花という漢字を書いて何と読むのか、その読み方や由来を紹介します。
魚へんに花と書いて「ホッケ」と読む「𩸽」の由来
魚へんに花と書いて𩸽を、「ホッケ」と読むようになった由来は以下の通りです。
・北海道の桜の花が咲く時期に脂がのる
・群れで泳ぐと花のように見える
・産卵期の雄に唐草模様が見られた
・法華経の「華」という漢字から
魚へんに花と書いて𩸽を、「ホッケ」と読むようになった由来は複数存在し、まず北海道の桜の咲く時期に脂がのることから、花という字が使われたという説です。ホッケの幼魚の体色は美しい青緑色をしていて、群れで泳ぐと花のように見えることも由来のひとつです。また産卵期のオスがコバルト色になり、鮮やかな唐草模様が見られることに由来する説もあります。
蝦夷地開拓時代に法華経を説いた僧侶は、ホッケの美味しさを広げたりそれまでいなかった魚を捕れるようにしました。このことから地元の人が「法華」と呼んだともいわれ、これが由来ともいわれています。
(*𩸽の漢字の由来について詳しく知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。)
魚へんに花と書く魚「ホッケ」はどんな魚?

ホッケはいつ頃が旬でどのくらいの大きさで、そして主にどの辺りに生息しているのでしょうか。ここではホッケがどのような魚なのか、生息地や旬の時期、栄養素等を紹介します。
ホッケは近年需要が高まってる
*表1
ーーーーーー
生息地/北海道近海/
大きさ/最大60cm/
旬/5~7月/11月
ーーーーーー
ホッケは主に北海道で獲れるものの鮮度の低下が早く、昔はまずい魚という印象でしたが、現在では流通や冷蔵技術が発達したため品質が安定しました。北海道近海でニシンが獲れなくなり、その代わりとして価格が手軽なホッケの需要が高まっています。成長の度合いは海域によって、25cm~60cmと大きな差が出ます。
ホッケは主に開き・干物として食されますが、5月から7月にかけて獲れるホッケが最高の干物となります。白身なので様々なアレンジが可能で、新鮮なものであれば刺身で食べることもできますが、アニサキスなどが寄生していることがあるため注意が必要です。
ホッケの栄養素
ホッケに含まれている主な栄養素は、以下の通りです。
・たんぱく質
・カルシウム
・ビタミンB12
・ナイアシン
・ビタミンD
・EPA
・DHA
血液や筋肉を構成する主要な成分であるたんぱく質は、エネルギー源として大切な栄養素でホッケに含まれるたんぱく質は体内で作ることができない必須アミノ酸を豊富に含んでいます。骨や歯を作る材料や筋肉の収縮・神経の興奮抑制を担うカルシウムも豊富です。
また、ナイアシンも多く含まれており糖質や脂質を燃やしエネルギーを作るときや、二日酔いの原因となるアルコール分解の際の酵素を助ける補酵素となります。DHAやEPAは中性脂肪や悪玉コレステロールを減らし動脈硬化予防や改善、脳卒中や高血圧など生活習慣病の予防に効果があります。DHAは認知症に、EPAはアトピーや花粉症の予防効果が期待できます。
(*ほっけの栄養素と効能について詳しく知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。)
𩸽以外に魚へんがつく漢字の魚は何がいる?由来は?
魚へんがつく漢字は、見たこともないような難しい漢字も含めて沢山あります。紹介してきた𩸽以外に、魚へんがつく漢字の魚とその由来を説明します。
①魚へんに末(䱅:いわな)