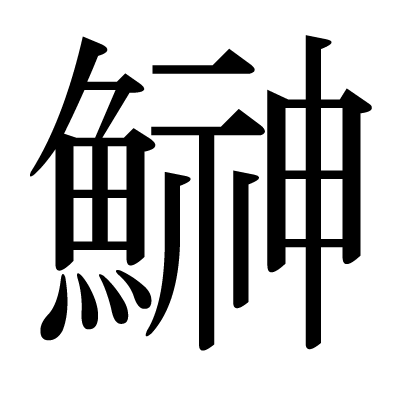魚へんに神「鰰」と書いて何と読む?意味・由来や他に魚へんがつく漢字は?
魚へんに神という漢字を書いてなんと読むか知っていますか?読み方は「ハタハタ」です。今回は、魚へんに神・雷で「ハタハタ」と読む由来をハタハタの特徴とともに紹介します。魚へんに暇と書く「鰕」など、魚へんがつく漢字の魚をハタハタ以外にも紹介するので参考にしてみてくださいね。
(このページにはPRリンクが含まれています)目次
魚へんに神という漢字を書いてなんと読む?読み方や由来とは?
魚の漢字には読み方が難しいものが多く、どのような魚を指すのか分からないことがあります。ここでは、魚へんに神と書く漢字の魚の読み方や漢字の由来を解説します。
魚へんに神と書いて「ハタハタ」と読む「鰰」の由来
鰰の読み方は「ハタハタ」で、ハタハタにこの漢字が当てられたのは雷神を意味する「霹靂神(はたたがみ)」に由来しています。ハタハタは冬の寒く雷が激しく鳴る時期に水揚げされることから、このような漢字が当てられました。
ハタハタの呼び方は、かつて雷が鳴り響くことを「はたたく」、雷の鳴る音を「はたはた」の擬音語で表現していたことから来ています。また、ハタハタのウロコが富士山のように見えることから、魚へんに神のつくりを合わせた漢字が使われるようになったとも言われています。
ハタハタは魚へんに「神」以外に「雷」と書くこともある
ハタハタは鰰と書くほか、雷のつくりを使った漢字や以下のように表記されることもあります。
・燭魚
・波多波多
・鱩
・雷魚
ハタハタは雷が鳴り響く季節に多く水揚げされることから、雷のつくりの漢字が使われることが多いです。また、ハタハタが水揚げされる時期の日本海は荒れており、波が多い様子から波多波多と表記されることもあります。
魚へんに神と書く魚「ハタハタ」はどんな魚?

魚へんに神と書くハタハタは短い期間しか漁獲できず、店頭で見たことがない人もいるかもしれません。ここでは、ハタハタの旬や水揚げされる地域などについて説明します。
ハタハタは秋田県の県魚
ハタハタは主に北日本海の浅瀬で漁獲される魚で、秋田県では県魚として有名ですが、島根県や鳥取県でも水揚げが行われシロハタとして親しまれています。ハタハタの漁獲時期は10月下旬〜1月ごろの冬で、このころに旬を迎える魚です。
ハタハタは夜行性の魚で、日中は砂の中に潜む性質があります。淡白な味わいのため、しょっつる鍋や田楽など、様々な調理方法で食べられています。
鰰以外に魚へんがつく漢字の魚は何がいる?
鰰以外に魚へんがつく漢字の魚には、どのようなものがあるのでしょうか。魚へんがつく漢字をもつ馴染み深い魚を由来とともに紹介するので、参考にしてください。
①魚へんに暇(鰕:エビ)

エビは、魚へんに暇の右側の文字を取って「鰕」と表記します。叚は体を曲げることを現すことを指し、エビが体を曲げる姿にちなんでこのような漢字が当てられるようになりました。また、エビを魚として扱うのは不適切といった考えにより、ヒキガエルを意味していた虫へんの「蝦」の漢字も用いられるようになった説があります。
(*エビの漢字表記について詳しく知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。)